
【試し読み】『放課後ミステリクラブ』100ページ分、無料公開中!
「放課後ミステリクラブ」シリーズの創刊を記念して、冒頭の「プロローグ」から「4 夜のおじぞうさん」の読者への挑戦状まで、無料の試し読みを公開いたします。名探偵・辻堂天馬の挑戦にキミは応えられるか? 続きが気になった方は、ぜひお手に取ってみてください。

『放課後ミステリクラブ 1金魚の泳ぐプール事件』
作 知念実希人 絵 Gurin.



プロローグ 事件発生
夜風が首すじを通りぬけていく。わか葉のかおりが鼻先をかすめた。
「もう夏ねぇ」
つぶやきながら真理子は天を見上げる。
さっきまで満月がうかんでいたが、いまは雲にかくれてしまっている。
うで時計に視線を落とすと、夜の十時をすぎていた。
「さて、お仕事お仕事」
スキップするように進んでいくと、フェンスにかこまれたプールが見えてきた。長さ十五メートル、はば十メートルほどの小さなプール。
真理子が先生をしている小学校で、水泳の授業に使われるプールだった。
明日からこのプールで水泳の授業が始まる。真理子が担任をしている四年一組の生徒たちが明日の午後、さいしょにこのプールで泳ぐことになっていた。
明日は暑くなりそうだし、みんなよろこぶだろうな。
真理子はフェンスにあるドアをくぐってプールのそばまで近づく。
あたりが暗いので、プールは底なしのあなが口を開けているかのようで気味が悪かった。
そのとき、フェンスの向こうがわのしげみから、ガサっという音が聞こえてきた。真理子は体をふるわせてそちらを向くが、暗くてよく見えなかった。
「きっと、風よね。早くすませちゃおう」
真理子は手に持っているビニールぶくろの中から、白いボール状のかたまりをとりだす。プールの消毒に使う塩素だった。
明日の水泳の授業のためにプールに水をため、消毒をしておく。そのために夜おそくまで学校に残っていた。
塩素ボールを投げこもうと大きくふりかぶったとき、急に雲が晴れたのか夜空に月があらわれた。暗かった水面がやわらかい光に照らされる。
真理子はかたまったまま、目をしばたたかせる。
プールの中で何かがキラキラと光っていた。
赤、黄色、白、だいだい色、もも色……。
色あざやかにかがやく小さな物体が、水面の下をゆったりと動いている。
それは金魚だった。
数十ぴきの小さな金魚が、プールの中を気持ちよさそうに泳ぎまわっている。
「なんで、金魚が……」
真理子はぼうぜんとつぶやいた。
あざやかな色をした金魚たちのうろこが、月光を乱反射する。
その光景はまるで、たくさんの宝石が泳いでいるかのように美しかった。

1 ミステリトリオ参上
「ねえ、陸もちゃんとゆかたを着てきてよ」
昼休み、美鈴ちゃんにそう言われたぼく、柚木陸は「えー」と声をあげる。
「えー、って何? お祭りに行くんだからゆかたを着るのは当然でしょ」
ぼくのつくえにすわった美鈴ちゃんこと神山美鈴は、ぼくの鼻先にいきおいよくひとさし指をつきつけた。ポニーテールにしたかみがゆれる。
となりの家に住んでいる美鈴ちゃんとぼくはおさななじみだ。同じようちえんに通い、小学校でも一年生のときからずっと同じクラスだった。
いつも元気で明るく、スポーツ万能の美鈴ちゃんはクラスの人気者だ。
ただ、ちょっと強引なところがあって、ときどきこまることもある。

けど、美鈴ちゃんの大きな目でじっと見つめられると、どうしても「いやだ」
とは言えなくなるのだ。
「わかったよ。お母さんにたのんでゆかた出してもらう」
「そうこなくっちゃ」
美鈴ちゃんはうれしそうにわらいながら、いきおいよく両手でつくえをおして飛びあがると、空中でくるりと一回転して着地した。長い手足をピンとのばして、ポーズをとる。
「……あぶないよ」
ため息をつきながら言うと、美鈴ちゃんはぼくのせなかを軽くたたいた。
「だいじょうぶだよ。わたしが失敗するわけないでしょ」
美鈴ちゃんはようちえんのころから体そうクラブに通っていて、大きな大会で何回も優勝している。いまも週に何回か、中学生や高校生にまじって、夜に体そうの練習に参加していた。
昨日から近くの神社でお祭りをやっているのだけど、練習があって美鈴ちゃんは参加できなかった。だから練習がない今夜、お祭りに行きたくてしかたがないのだ。
「ねえ、天馬君もいっしょにお祭り行こうよ。きっと楽しいよ」
美鈴ちゃんはとなりの席で本を読んでいる天馬君、辻堂天馬に声をかける。
天馬君は手にしていた本にしおりをはさんでとじると、つくえの上に置いた。
表紙には『バスカヴィル家の犬』
と書かれている。
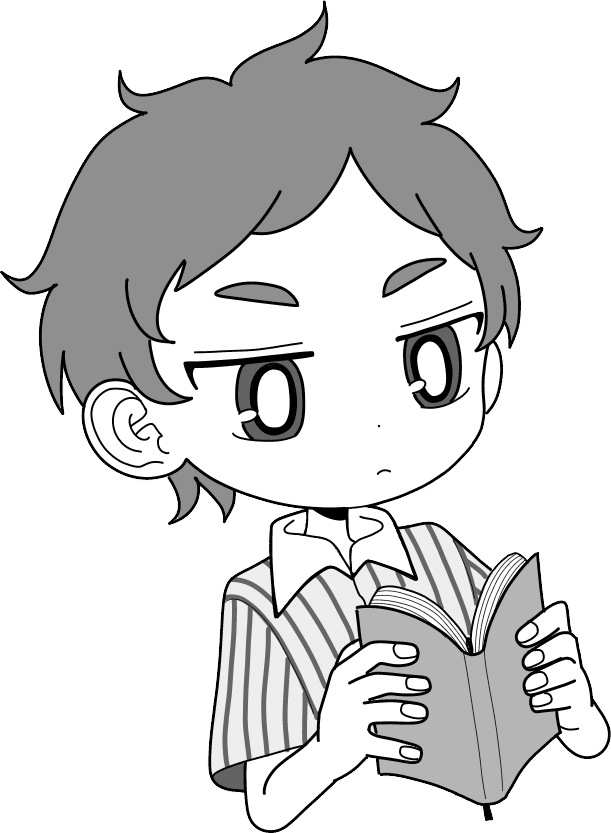
天馬君はいつも、ぼくたちが読む子ども用の本ではなく、おとな向けのむずかしそうな文庫本を読んでいた。
「悪いけど美鈴君、えんりょしておくよ。読みたい本があるから」
天馬君はかたをすくめる。
天馬君は相手が女子でも、なかよくなると『君』をつけてよぶ。去年転校してきた天馬君は、それまでイギリスにいて、日本語は本を読んで覚えていたせいか、しゃべりかたがすこしおとなっぽかった。
「えー、つまんない」
美鈴ちゃんはくちびるをとがらせる。
「それじゃあ陸、今日の夕方、神社の前で待ちあわせだから、わすれないでよ。天馬君もその本読み終わったらいっしょに行こうよ」
「うーん、気が向いたらね」
天馬君は明らかにやる気のない口調で言った。
美鈴ちゃん、天馬君、そしてぼくの三人は、去年から同じクラスで、席も近かった。だから、いつも三人で遊んだり、勉強をしたりしている。
それに、ぼくたち三人には、ちょっとしたひみつがある。
そのとき、スピーカーからチャイムが聞こえてきた。昼休みが終わる十分前の予鈴だ。今日はスープを入れるための大きななべがひとつ行方不明になっていたとかで、給食の時間がおくれた。そのせいで、昼休みが短く感じる。
「美鈴ちゃん、天馬君、そろそろ更衣室に行かないと。次、水泳の授業だよ」
ぼくが声をかけると、美鈴ちゃんはひらひらと手をふった。
「あと十分もあるじゃん。待ちあわせ時間を決めてからでもまにあうよ」
「でも、女子は水着に着がえるのに時間がかかるじゃないか」
みんな水泳の授業を楽しみにしていたので、ほとんどの生徒が給食を食べてすぐに更衣室に行っていた。
教室にはぼくたちをあわせて五人しか残っていない。
「だいじょうぶだいじょうぶ。プールが楽しみすぎて、服の下に水着を着てきたから」
わらって言った美鈴ちゃんは、「あっ」と声をあげて教室のすみを見る。
そこには長いかみをみつあみにした女の子がすわっていた。
同じクラスの早乙女華さんだ。いつもはピンクとかブルーのあわい色のスカートを着ていることが多いけど、今日は黒いズボンをはいている。
「ねえ、華ちゃんもいっしょにお祭りに行かない?」
美鈴ちゃんが早乙女さんをさそう。
四年生になるまでちがうクラスだったので、ぼくは早乙女さんとあまり話したことがないのだけど、だれとでもすぐなかよくなる美鈴ちゃんは、もう友だちになっていた。

スポーツ万能で活発な美鈴ちゃんと、体が弱くてよくかぜをひいて学校を休んでいる早乙女さんはぜんぜんちがうタイプだけど、気が合うらしい。
「ごめんなさい、美鈴ちゃん。今日はちょっと……」
「あ、もしかして今日もピアノのレッスン?」
早乙女さんはピアノを習っていて、この前、家に遊びに行った美鈴ちゃんは
「おうちにグランドピアノがあるんだよ。すごくない!?」とはしゃいでいた。
「ううん、ピアノの練習はお休み。ちょっと手をケガしちゃって」
首をすくめて早乙女さんは言う。
たしかに手の甲に、小さな赤いきずが何本か走っていた。
「練習ないならさ、いっしょに行こうよ。みんなで行ったほうが楽しいじゃん」
「でも……、おこづかいがほとんどなくて……」
早乙女さんはもじもじとする。
「やめろよ。華がこまっているだろ。みんな、こづかいなんてもらったらすぐにマンガとかおかしにつかって、残っていないんだよ」
うしろのほうから、大きな声が聞こえてきた。
ふりかえると重田太一君が、つくえに足をのせてこちらを見ていた。
「それって、重田君だけでしょ。華ちゃんとは関係ないじゃない」
クラスでいちばん体が大きく、少しらんぼうなところがある重田君は、美鈴ちゃんとあまりなかがよくなかった。何度か言いあらそいをして、ふたりして先生におこられている。
「関係あるんだよ。華がいやがっているんだから」
たしかぼくと美鈴ちゃんと同じように、重田君と早乙女さんも家がとなりどうしのおさななじみだったはずだ。四年生になってすぐ、気の弱い早乙女さんが男子にからかわれていたときは、すぐに重田君が助けに入っていた。それ以来、早乙女さんがからかわれたりすることはない。
「なによ、華ちゃんが自分のものみたいに言ってさ。そういうらんぼうな言いかたをするから、女子からこわがられるんじゃん」
「なんだと」
いすから立ちあがった重田君はつかつかと近づいてくる。

男子でいちばん身長が高い重田君と、女子でいちばん身長が高い美鈴ちゃんはおでこがつきそうなくらい近よってにらみあった。
ぼくと早乙女さんはどうすればいいかこまってあたりを見まわしたけど、天馬君は興味なさそうにまた文庫本を読み始める。
「ちょ、ちょっとふたりとも、やめなって。また先生にしかられるよ」
しょうがないので、ぼくは強引にふたりのあいだに入って引きはがす。
「柚木……」
重田君は美鈴ちゃんのかわりにぼくをにらんだ。
十センチ以上、身長が高い重田君を前にして、ぼくはごくりとつばを飲む。
重田君はチッと舌打ちすると、身をひるがえした。
「ミステリトリオなんかにかまってられるかよ」
「そのよびかたやめてって、何度も言ってるでしょ!」
美鈴ちゃんがもんくを言うけど、重田君はムシして自分の席にもどっていった。

美鈴ちゃんの「みす」
天馬くんの「て」
そしてぼくの名前、陸の「り」をとって
ぼくたち三人のことを『ミステリトリオ』とよぶクラスメートがいる。
重田君もそのひとりだった。
べつにぼくは気にならないんだけど、美鈴ちゃんはそうよばれることがいやなのだ。
「いいじゃないか、美鈴君。ミステリトリオ、悪くないひびきだと思うよ」
天馬君が楽しそうに言うと、美鈴ちゃんはほおをふくらませた。
「ミステリオタクの天馬君はいいかもしれないけど、わたしはいやなの。ミステリって『ふしぎ』とかそういう意味でしょ。なんか『ふしぎちゃん』ってバカにされているような気がして。陸もそう思うでしょ」
急に話をふられたぼくは、「え、いや、それは……」としどろもどろになってしまう。美鈴ちゃんはさらにほっぺたをフグのようにふくらませた。
「それより、さすがにそろそろ更衣室行かないと、おくれちゃうよ」
ぼくがごまかすように言うと、天馬君は読んでいた本をとじた。
「そうだね。名探偵が真実を明らかにするところだったんでちょっと残念だけど、ちこくしてしかられたらこまるしね」
天馬君が本をカバンにしまったとき、急にとびらが開いて、先に更衣室に行っていたはずのクラスメートたちがぞろぞろともどってきた。
「あれ、みんなどうしたの?」
美鈴ちゃんがたずねると、男子のひとりが大きく手をふった。
「今日のプール中止だってさ」
「えー!」
美鈴ちゃんが、不満の声をあげる。
そのとき、ぼくたちのクラスの担任の真理子先生が教室に入ってきた。
「はい、みんな着席。静かにしてねー」
黒板の前に立った真理子先生がはくしゅをするように手を鳴らす。ぼくたちは言われたとおり、席に着く。
「残念だけど、今日のプールは中止になりました。次の授業は自習になります」
プールを楽しみにしていたたくさんの生徒のガッカリの声と、そんなに楽しみにしていなかった少しの生徒のはしゃいだ声がまじりあう。見ると、重田君もけわしい表情で口をかたく結んでいた。

水泳が、というか運動が全体的にとくいじゃないぼくも、どちらかというとうれしかった。暑い日にプールに入るのは気持ちいいんだけど、終わったあと、どっとつかれてねむくなってしまうのだ。
となりの席を見ると、天馬君がいそいそとカバンから本をとり出していた。
小説の続きが読めるのがうれしいんだろう。口もとがゆるんでいる。
「どうして水泳できないんですかぁ。ずっと楽しみにしていたのに」
ふりむくと、うしろの席の美鈴ちゃんがいすからこしをうかして、手をあげていた。
「ごめんね、美鈴ちゃん。ちょっとプールに問題があって。来週の授業はできるからがまんしてね」
真理子先生は顔の前で両手を合わせる。
そのとき、ふとぼくは、天馬君が本をつくえに置いたまま、読み始めていないことに気づいた。
切れ長のその目は、まっすぐに真理子先生を見ている。しんけんなその表情を、ぼくはこれまで何度も見ていた。天馬君が『ナゾ』を見つけたときの表情。

「どうしたの、天馬君。本の続きを読むんじゃないの?」
小声でたずねると、天馬君はあごに手をそえた。
「いや、ちょっと気になることがあってね」
「気になることって?」
「真理子先生はいま、『ちょっとプールに問題があって』って言ったよね」
「それがどうしたの? どこか故障したんじゃないの。水を入れる機械とか」
「だとしたら、『プールがこわれて』とか『機械が故障して』って言うと思う。けれど、真理子先生は『ちょっとプールに問題が』って、わざとあいまいな言いかたをしていた気がする。つまり、その『問題』というのは、ふつうでは起こらないことなのかもしれない」
わかりやすい天馬君の説明に、ぼくは「なるほど」とうなずく。
「何コソコソと話してるの? わたしにも教えてよ」
うしろの席から美鈴ちゃんが声をかけてくる。
「いや、天馬君がね……」
ぼくが説明しようとしたとき、スピーカーからまたチャイムの音が聞こえてきた。授業開始の本鈴だ。
「はーい、それじゃあ自習始め。私語はしちゃだめよ」
真理子先生がまた両手を鳴らす。
天馬君は外国の映画で俳優さんがやるように大きくかたをすくめると、つくえに置いていた本を読み始めた。
2 ひみつきちの三人
「えー、そんなの気にしすぎじゃない?」
いすに前後ぎゃくにすわって、背もたれに両うでをのせている美鈴ちゃんが声をあげる。
「ふつうの人が気づかないような、ささいなできごとから真実をみちびいていくのが、名探偵という存在なんだよ」
天馬君はとくいげに言いながら、顔の横でひとさし指を立てた。
放課後、ぼくたちは四階建ての校舎のいちばん上の階の、さらにいちばんおくにある小さな部室にいた。
去年までは倉庫として使われていた小さな部屋だけど、三人でいっしょうけんめいそうじして、いろいろなものを持ちこんでいた。
天井までとどく大きな本だなには、天馬君が持ってきた大量のミステリ小説がつまっている。
ほかにも天馬君は、部屋のおくにテーブルを置いて、そこに理科室にあるようなビーカーやフラスコ、アルコールランプなどを用意し、ときどき何かあやしい実験をしている。
美鈴ちゃんは小さなトランポリンと、体そう用の鉄棒を持ちこんでいて、よくそれではねたり、逆上がりしたりしていた。
ぼくが最初に持ってきたものは、マンガぐらいだった。
けど、半年ぐらい前に、バーとかいうおとながお酒を飲むお店の店長をやっているしんせきのおじさんがお店を改装するというので、いらなくなったものをくれた。
それが、ジュークボックスというおしゃれな機械だった。
せんようのコインを入れてボタンをおすと、中に入っているレコードとかいうものが自動的にセットされて音楽を流してくれる。ぼくたちは知らない、昔の海外の曲ばかりだけど、流しているとなんだか気持ちいいので、いつも使っている。

それに、おじさんはバーカウンターも運びこんでくれた。おとなの人がお酒を飲むときに使うカウンターといすにすわって、ぼくたちはよくジュースを飲んだり、おかしを食べたりしている。
この小さな部室は、ぼくたちにとってまさに『ひみつきち』だった。
この小学校の規則ではクラブ活動に参加する生徒以外は授業が終わったあと、図書館以外の校内に残ることはできない。
けれど、夕方から学校の近くにある体そうクラブで練習をする美鈴ちゃんをはじめ、ぼくたち三人には放課後、学校で時間をつぶさなくてはいけない事情があった。
前は図書館で本を読んだり、宿題をしたりしてすごしていたのだけど、こわい司書さんがいるので話をしたり、おかしを食べたりすることはできなくてつまらなかった。
けれど去年、あるできごとがあってからはこの部屋を使うことができるようになり、それぞれ好きなことをしながらすごせるようになっていた。
せまくて少しカビくさいけど、ぼくはひみつきちのようなこの部屋が好きだった。

「真実をみちびいていくって、天馬君、なんでプールが使えなかったのか、わかったの?」
からかうように美鈴ちゃんが言う。
「わかるわけないじゃないか。まだまだ情報不足だよ。真実というのはね、多くの情報をつなぎあわせて、初めてその全体像が見えてくるものなんだよ」
「なら、その情報をさがしに行こうよ。お祭りまではまだ時間あるしさ」
今日は体そうの練習がないので、美鈴ちゃんはもう家に帰ってもいいはずだし、じつはぼくもそうなのだけど、放課後はここに三人で集まるのがなんとなくあたりまえになっていた。
ただ、本を読むのが好きな天馬君や、家に帰ってからゲームをするためにここで宿題を終わらせているぼくとちがって、美鈴ちゃんはじっとしていられないせいかくだ。だから、少しでもひまつぶしになりそうなことを見つけては、ぼくたちをさそうのだ。
「そんな必要はないよ」
天馬君は立てたひとさし指を左右にふる。
「本当に何かおかしなことが起こったなら、情報は自然とやってくる。ぼくたちはここで待っていればいいのさ」
「そんなのたいくつ!」
美鈴ちゃんがもんくを言うと、天馬君は部屋のすみにある本だなを指さした。
天井までとどきそうなほどの大きな本だなには、ぎっしりと本がつまっている。ぼくや美鈴ちゃんが持ってきたマンガも少しあるけれど、大部分は天馬君が家から運んできたミステリ小説だ。
「いつも言っているじゃないか。えんりょしないで、そこにある本を読んでいいって。初心者におすすめは、なんといってもシャーロック・ホームズのシリーズだね。ただ、キャラクターのみりょくよりもミステリとしてのおもしろさを求めるなら、アガサ・クリスティが……」
美鈴ちゃんがつまらなそうな表情をうかべていると、ろうかから足音が聞こえてきた。
「ほら、来た」
天馬君がとくいげに言う。
次のしゅんかん、とびらがいきおいよく開き、真理子先生が入ってきた。
「待ってましたよ、真理子先生。どうぞすわってください」
「待ってた?」
真理子先生がふしぎそうに言う。
「ぼくたちに何か相談があるんですよね。合言葉をわすれて入ってきてしまうぐらいあわてるとは、何があったんですか? くわしく教えてください」
天馬君が言うと、真理子先生はいっしゅん目を大きく見開いたあと、大きくため息をついた。
「あいかわらず、天馬君はなんでもお見とおしね。でも、できればその才能で、昨日たのんだ事件も解決してほしいんだけど」
「あれですかぁ?」
とたんに天馬君のテンションが落ちた。
三日前、体育館のそばに置かれているおじぞうさんがだれかにたおされるという事件があった。百五十年以上前、江戸時代に作られたおじぞうさんで、とてもきちょうなものらしい。
うちの小学校では生徒にいたずらされたりしないよう、ブロックべいでかこって、かぎのかかったとびらを開けないとおじぞうさんには近よれないようになっていた。

きちょうなおじぞうさんがたおされたことは大きな問題になって、昨日の朝礼では校長先生が「絶対にそんなことをしてはいけません!」と全校生徒に言っていた。
「あんなの、だれかがへいをよじ登って中に入って、いたずらしただけに決まっているじゃないですか」
「だから、天馬君たちにそのいたずらをした犯人を見つけてほしいの。またあんなことがあったらこまるから。なんと言ってもあなたたち、『ミステリクラブ』でしょ」
真理子先生はにっこりとほほえむ。
クラブ活動以外では放課後、校内に残れないという規則なので、ぼくたち三人は『ミステリクラブ』というクラブ活動に所属して、この部屋を使っているということになっていた。顧問は真理子先生だ。
「真理子先生、ミステリクラブの活動は、つまらない事件を追うことじゃあ
りません。こうして、ミステリ小説を読んで、人類の英知とも言えるこの高尚な知的ゲームに興じ、自らの知性を磨くことなんです」
なんだかむずかしい言葉をならべ立てながら、天馬君は手にしていた本をかかげた。そこには『そして誰もいなくなった』と書かれていた。
「でも、美鈴ちゃんと陸君がミステリ小説を読んでいるところ、一度も見たことがないんだけど。このままだと、『ミステリクラブ』って、あなたたちの名前からとっただけだと思われるわよ。『ミステリトリオ』の三人さん」
真理子先生がからかうように言う。『ミステリトリオ』とよばれることをきらっている美鈴ちゃんが顔をしかめた。
「美鈴君と陸君には何度もすすめているんですけど、全然読んでくれないんですよ。なんでこの楽しさを理解してくれないんだろうなぁ」
天馬君はしょんぼりとする。
「それなら、やっぱりミステリクラブの活動は、事件を解決することじゃない。いままでもいろいろな事件を解き明かしてくれたでしょ」
真理子先生の言うとおり、天馬君はこれまで、この学校で起こったふしぎな事件をいくつも解決していた。そして、そのときは美鈴ちゃんとぼくも、その事件のナゾ解きに協力するのだ。
さいしょに天馬君が解決した事件は去年、真理子先生が生徒のみんなから集めたはずの給食代が、それを入れていたキラキラのペンケースごと消えた事件だった。
夕方、図書室をあとにして帰ろうとしていたぼくたちは、教室でよつんばいになって先生用のつくえの下をさがしている真理子先生を見つけた。
事情を聞いた天馬君は職員室に向かい、給食代を入れたケースを置いていたはずだという真理子先生のつくえのまわりを調べた。そして、開いているまどに近づくと、すぐそばにある大きな木を指さして言った。
「きっとあそこです」
身軽な美鈴ちゃんが木に登って調べたところ、そこにあるカラスの巣の中に、給食代が入ったケースがあった。
「カラスは光るものにひかれる習性があるんです。だから、開いているまど
からキラキラのケースを見つけたカラスは、職員室にだれもいないとき、それを巣に持って帰ったんですよ」
天馬君はとくいげにそう言ったのだった。

その事件のお礼として、真理子先生は『ミステリクラブ』の顧問になってくれることになり、ぼくたちは放課後の時間をすごす部室を手に入れることができたのだ。
「これまでぼくたちが解き明かしてきた事件は、どれもみりょくてきなナゾがあるものでした。それに対し、おじぞうさんがたおされた事件にはなんのナゾもありません」
「けど、先週から生徒たちのあいだで、『おじぞうさんが泣いている声がする』ってうわさが流れていたのよ。あなたたちも知っているでしょ」
たしかに、クラスメートがそんなことを言っていた気がする。
「そんなの、風の音か何かですよ」
天馬君は興味なさそうにつぶやいた。
「あ、天馬君、もしかして自信がないのかな? 最近、あまり事件を解いていなかったから、じまんの推理力が落ちているんじゃないの?」
天馬君をたきつけるように、真理子先生は言う。
天馬君は手にしていた文庫本をとじた。
「美鈴君、さっきキミは早乙女さんをお祭りにさそったけど、『おこづかいがほとんどなくて』ってことわられたよね」
「え? うん、そうだけど、それがどうしたの?」
急に声をかけられた美鈴ちゃんは、ふしぎそうにまばたきをする。
「どうして早乙女さんのおこづかいがないのかわかるかな? かなりのスペースをとり、さらに何百万円もするグランドピアノが家にあるということは、早乙女さんの家は、かなりお金持ちなはずだ。おこづかいもけっして少なくはないだろう。それに、早乙女さんはそんなにむだづかいをするタイプじゃない。美鈴君のように、帰り道に買い食いをしたりしているのは見たことがないし」
「美鈴ちゃん、そんなことしているの?」
真理子先生ににらまれた美鈴ちゃんは、「それでそれで?」と天馬君に先をうながして、ごまかそうとする。
「つまり最近、おこづかいをたくさん使うようなできごとがあったということだよね。さて、それがなんだかわかるかな?」
天馬君はぼくたちの顔を順番に見まわした。
ぼくたちはとまどっておたがいに顔を見あわせる。
「えっと、天馬君にはわかるの?」
ぼくがおずおずとたずねると、天馬君は「もちろん」とむねをはった。
「早乙女さんはネコをかい始めたんだよ」
「ネコ?」
どうして急にネコが出てきたのかわからなくて、美鈴ちゃん、真理子先生、ぼくの三人の声が重なった。
「そう、子ネコだろうね。たぶん、黒ネコだよ」
「なんで子ネコが出てくるの? 華ちゃん、そんなこと言っていなかったでしょ」
美鈴ちゃんがたずねる。天馬君はくちびるのはしをあげた。
「いや、言っていたよ。たしかに言葉には出していなかったけど、ぼくの目から見れば、早乙女さんは『黒い子ネコをかい始めました』って全身で語っていたんだ」
「全身で?」
美鈴ちゃんが首をひねると、天馬君は大きくうなずいた。
「早乙女さんは手をケガして、ピアノのレッスンを休むと言っていたね。そして、手の甲に小さなきずがいくつかあった。あのようなきずはネコに引っかかれてつくことが多い」
「そうとはかぎらないんじゃないかな。たとえばさ、野球とかをしていて草むらにボールが入りこんだときとか、よく手の甲に小さなきずがつくよ」
ぼくが言うと、天馬君は大きくかたをすくめた。

「あの早乙女さんが、雑草をかきわけてボールをさがすと思うかい? それに、早乙女さんがめずらしくズボンをはいてきたのも、子ネコをかい始めたという推理をうらづけるものだよ」
天馬君は足を組んだ。
もともと、おとなっぽい口調の天馬君だけど、いまみたいに推理をひろうするときは、さらに子どもらしくない態度になる。ただ、ぼくはそのすがたが、海外ドラマを見ているようでなんとなく好きだった。
「なんで早乙女さんがズボンをはいてきたら、ネコをかったことになるの?」
真理子先生が首をひねる。
「ネコに引っかかれやすいのは、なでたりする手だけではなく、ネコの目の高さにある足もだからですよ。つまり、早乙女さんは足にも引っかかれたきずがあったんだと思います。スカートだといくら長くても、足を全てかくすのはむずかしい。だから、早乙女さんはめずらしく、今日はズボンすがただったんですよ」
天馬君の説明に、真理子先生は「なるほど」とあごを引いた。
「でもさ、どうして子ネコだってわかるの?」
美鈴ちゃんが身を乗り出す。
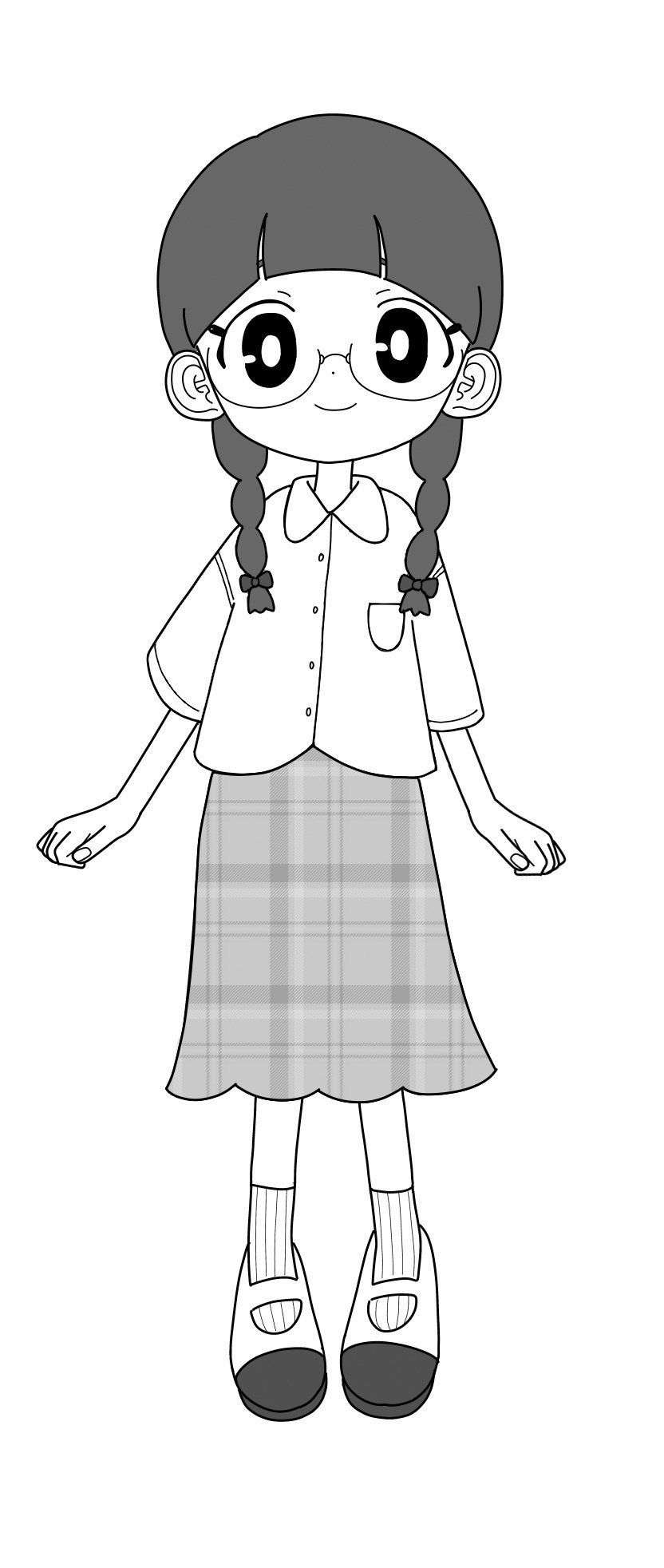
「それはかんたんさ。早乙女さんの手の甲についたきずは、とてもうすかった。もしおとなのネコならあのていどではすまないよ。体が小さく、力が弱い子ネコによるものだね」
「じゃあ、黒ネコだっていうのは?」
美鈴ちゃんに続いてたずねたぼくに、天馬君が視線を送ってくる。
「陸君はネコをかったことがないんだね。ネコという生き物はね、想像よりはるかに毛がぬけるんだ。足もとにまとわりつかれたりしたら、ズボンが毛だらけになるくらいにね」
「あっ!? だから、華ちゃんが今日、黒いズボンをはいていたのって……」
美鈴ちゃんが両手を合わせる。
天馬君は満足そうに首をたてにふった。
「そう、ネコの毛が目立たないようにさ。黒い毛がね」
あざやかな推理にぼくたちが言葉をうしなっていると、天馬君は立ちあがって真理子先生の前までやってくる。
「これで、推理力が心配だからぼくが事件の捜査を引き受けようとしないといううたがいは晴れたでしょ」
「はいはい、わたしがまちがっていました、名探偵君」
真理子先生は両手を軽くあげる。
『名探偵』とよばれた天馬君は、うれしそうにはにかんだ。
「それじゃあ、その名探偵君のおめがねにかなうようなふしぎな事件が起こったの。だから、ちょっと知恵をかしてくれないかな?」
「もちろんです。では、プールに行きましょう」
天馬君はスタスタと出入り口に向かった。
「え? なんでプールのことだってわかるの⁉」
真理子先生がおどろいて言うと、天馬君はふりかえってウインクをした。
「だってぼく、名探偵ですから」
「わあ、これはすごいですね」
プールサイドに立った天馬君がはしゃいだ声をあげる。
ぼくはあぜんとして、数十ぴきの色あざやかな金魚が泳ぐプールをながめた。
ふと横を見ると、美鈴ちゃんも口を半開きにしてかたまっている。
「これが、水泳の授業ができなかった理由なんですね」
ふりかえった天馬君が、真理子先生に声をかける。
「うん、まさか、こんなじょうたいで生徒を泳がすわけにはいかないからね」
「けど、どうして『ちょっと問題が』なんてぼやかしたんですか?」
「プールに金魚がいますなんて言ったら、みんなきょうみをもっておしかけるでしょ。きっと、うわさが広まって学校に関係ない人まで見学に来ようとする」
「なるほど、できるだけさわぎはさけたいですからね。それで、ぼくに捜査をしてほしいってことですね」

目の前に広がるふかしぎなできごとにこうふんしているのか、天馬君は早口でまくし立てた。
「そう、だれがなんのためにこんないたずらをしたのか、わからないと気味が悪いから。どう、何か気づいたことある?」
真理子先生は身を乗り出してくる。
「そうあせらないでくださいよ。推理するにも、まだ何も情報がないんです。ところで、この金魚、どうするんですか?」
「このあと、先生たちですくうことになってる。このままじゃ、明日からの水泳の授業にも使えないから」
真理子先生はつかれた口調で言った。
「水泳は週に一回しかない特別な授業ですからね。すごく楽しみにしている生徒も多いし。けど、明日からプールが使えるということは、ぼくたちのクラスだけが中止になったということか……」
つぶやきながら、天馬君は水面に顔を近づける。
「そんなに大きな金魚じゃないですね。ただ、何十ぴきもいる。これだけの数を運ぶのは、かなりたいへんだったはずだ。生きたまま運ぶためには、水もいっしょに運んでこないといけないから」
プールからはなれ、フェンスに近づいた天馬君は、「ああ、あれだ」と外を指さす。フェンスの向こうがわの草むらに、かくされるように台車が置かれていた。

そのそばには大きななべが転がっている。
「あ、昨日、プールを消毒しようとしたとき、何か音がしたあたり!?」
真理子先生が声をあげる。
「もしかしてあれって、なくなっていたっていう給食用のなべ?」
ぼくが声をあげると、天馬君はうなずいた。
「うん、きっとそうだね。犯人はあのなべに金魚を入れてここまで運んだんだ。台車も体育館のそばの倉庫とかにあったやつだろうね。本当ならふたつとも元の場所にもどしておきたかったけど、金魚をプールに入れてすぐに真理子先生が来たから、置きっぱなしであわててにげたんだよ」
そこで言葉を切った天馬君は、うでを組んで数十秒考えこんだあと、いきおいよく顔をあげた。
「美鈴君!」
急に大きな声をかけられた美鈴ちゃんは「な、何?」とそりかえる。
天馬君は大きく手を広げた。
「気が変わったよ。今夜、ぜひ三人でお祭りに行こう。日本のお祭りというやつをぜひ見てみたいからさ」
3 お祭りの夜
鳥居のおくの石だたみ、その両がわに屋台がならんでいる。
多くの人々が、ちょうちんの明かりに照らされながら、屋台でやきそばやたこやき、わたあめを買ったり、射的やかたぬきを楽しんだりしている。
プールの金魚を見た日の夜七時、ぼくたち三人は学校の近くにある神社の前で待ちあわせをしていた。
「うわあ、すごい人。やっぱりお祭りはこうでなくっちゃね!」
お祭りとかのイベントが大好きで、はしゃいだ声をあげる美鈴ちゃんは、花がらの入った赤いゆかたを着ていた。それに対してぼくは、タンスのおくから引っぱり出した地味な紺色のゆかただ。
「ところで……」
一転して低い声で言いながら、美鈴ちゃんはとなりに立つ天馬君をジトッとした目で見る。
「どうして天馬君は、そんなかっこうしてるの?」
「何度も言っているじゃないか。これが探偵のユニフォームだからだよ」
とくいげにむねをそらす天馬君は、おとなの人が着るような、茶色いチェックのコートをはおり、同じもようのつばの小さなぼうしをかぶっていた。天馬君が好きなシャーロック・ホームズとかいう名探偵の服をまねているらしい。
「そうじゃなくて、ゆかたを着てきてって言ったでしょ。お祭りを楽しむユニフォームはゆかたなんだよ」
美鈴ちゃんのこうぎに、天馬君は頭をかく。
「そう言われても、ぼくの家にゆかたなんてないんだよ。イギリスから持ってきた服以外は、あまり買ってもらっていないから」

「あ……そっか。ごめんね」
ハッとした表情になって、美鈴ちゃんはあやまった。
お父さんとお母さんが別れて、天馬君はイギリスから日本にもどってきた。お母さんは仕事でおそく帰ってくるので、早く帰るととても広い家にひとりぼっちになる。だから、天馬君はできるだけ学校にいるのだ。
「けど天馬君、そのかっこう、暑くないの?」
ぼくがたずねると天馬君はその場でいきおいよく一回転した。
コートのすそがひらりと風を切る。
「暑くなんかないよ。この服を着ると『ナゾ』に集中できて、暑さも寒さも感じなくなるんだ」
ちょうちんの光に照らされる天馬君のおでこにあせが光っている気がするが、ぼくは見なかったことにする。

「それじゃあさ、どの屋台から見る? わたしね、りんごあめ食べたい」
気をとり直すように美鈴ちゃんが明るい声をあげた。
「何を言っているんだよ、美鈴君。なんのためにお祭りに来たと思っているんだい?」
「なんのためって、お祭りを三人で楽しむためでしょ?」
美鈴ちゃんが小首をかしげると、天馬君は「ちがうちがう」と大きく手をふった。
「捜査をするために決まっているじゃないか」
「捜査って、もしかして『金魚の泳ぐプール事件』のこと?」
ぼくがしつもんすると、天馬君は「もちろん」とうなずく。
「プールのあれと、お祭りの何が関係あるの?」
両手をこしにあてる美鈴ちゃんに、天馬君はにこにこしながら、何か耳打ちする。美鈴ちゃんの目が大きくなった。
「それじゃあ、あの金魚って……」
「たぶんね。というわけで、美鈴君、お願いできるかな?」
美鈴ちゃんは「はーい」と言うと、神社に向かって歩いていく。
「美鈴ちゃんに何をお願いしたの?」
ぼくは美鈴ちゃんのあとに続きながら、となりを歩く天馬君にたずねる。天馬君は「すぐにわかるよ」といたずらっぽく答えた。
鳥居をくぐる。境内の参道はぎゅうぎゅうにこんでいた。
「これじゃあ、前に進めないよ」
人波にもまれるぼくに、美鈴ちゃんは「こっちこっち」とふたつの屋台のあいだにある小さなすきまを指さす。そこを通って屋台のうら手に出ると、大きな木がたくさんはえている林になっていた。参道とちがって、ここにはだれもいない。
「じゃあ、ちょっと待っててね」
美鈴ちゃんはとつぜん、ゆかたのすそをひざまでまくると、そばにはえていた大きな木のみきに飛びついた。両手足を器用に使いながら、美鈴ちゃんはリスのようにするすると身軽に木を登っていく。
小さなときから体そうを習っていた美鈴ちゃんにとって、木登りぐらいお手のものだ。この前なんて、一階から校舎の屋上まで、かべをつたって十秒ぐらいで登って、真理子先生に大目玉をくらっていた。
十メートルくらいの高さまで登った美鈴ちゃんは、太いえだにこしかける。
「美鈴君、見つけたかい?」
見あげながら天馬君がたずねると、美鈴ちゃんが「あった!」と、参道のおくを指さした。
「おくから三番目にあるよ」
美鈴ちゃんは、ひょいっとすわっていたえだから飛びおりる。
「あぶない!」
ぼくが声をあげると、美鈴ちゃんはえだをつかんで、てつぼうのようにきれいに逆あがりをしていきおいをころしたあと、手をはなしてすぐ下にあるえだへと移動した。
ゆかたを着た体を前後にふっていきおいをつけては、美鈴ちゃんは次々にえだからえだへと飛びうつりながらおりてくる。
ちょうちんの光に照らされた赤いゆかたがきれいだった。

「とうちゃっく!」
美鈴ちゃんは足をピンとのばし、両うでをななめ四十五度にあげて着地を決める。
「さすがは美鈴君。すごい運動神経だね」
天馬君がはくしゅをすると、ゆかたのすそを元にもどしながら美鈴ちゃんは
「すごいでしょ」とにっこりわらった。
「でも、美鈴ちゃん、あぶないよ。手をすべらせたらケガするよ」
ぼくは口をへの字にする。
「だいじょうぶだいじょうぶ、わたしがそんなヘマするわけないじゃない。陸って本当に心配性だよね。それより、せっかく見つけたんだから、早く行こうよ」
美鈴ちゃんはぼくの手をつかんで引っぱり始めた。
「ちょ、ちょっと、行くってどこに?」
引きずられながらたずねると、美鈴ちゃんのかわりに、天馬君が「すぐにわかるよ」といたずらっぽく答えた。
ぼくたち三人は、ならんだ屋台のうしろを進んでいくと、またテントとテントのすきまを通って参道にもどる。鳥居の近くにくらべると、このあたりはまだ人が少なかった。
「あの屋台だよ」
天馬君が指さした先には、『金魚すくい』と書かれた大きなかんばんをかかげた屋台があった。
「金魚すくい……。もしかして、あのプールの金魚って……」
「それをたしかめるんだよ。さあ、陸君、美鈴君、行こう」
天馬君は人ごみをかきわけて、金魚すくいの屋台へ向かった。
「へい、いらっしゃい!」
屋台の前に来ると、はげあがった頭にはちまきをまいた店主の男の人が、いせいのいい声をあげた。店主の前には、プラスチックのすいそうが置かれて、金魚が泳いでいる。
「どうだい、金魚すくいやっていかないかい。一回三百円だよ」
「金魚、少ないですね」
すいそうの前にしゃがみこんだ天馬君がつぶやく。
たしかに、それなりに大きなすいそうなのに、金魚は三十ぴきくらいしかいなくて、少しさびしい感じがした。
そのせいか、ぼくたち以外にお客さんもいない。
「これだけいればじゅうぶんだろ。それで、やるのか、やらないのか?」
店主はちょっとイライラした口調で言う。
「やりますよ。三人分お願いします」
天馬君の答えを聞いて、ぼくと美鈴ちゃんは「え!?」と声を重ねた。
「天馬君、お話を聞きにきたんじゃないの?」
「ちょっと天馬君、わたし、あんまりおこづかい持ってきてないの。あとで、りんごあめとかたこやき食べるお金がなくなっちゃう」
ぼくたちのもんくを聞き流した天馬君は、コートのポケットから千円札をとり出して店主にわたしながら、ふりかえってほほえんでくる。
「いいからいいから、せっかくお祭りにきたんだから、三人で楽しもうよ」
店主が「まいどあり!」とポイをみっつと、おつりの百円玉を天馬君に手わたした。
「実は金魚すくいをするのは初めてなんだ。美鈴君、陸君、お手本を見せてよ」
天馬君はぼくたちにポイをひとつずつおしつけてくる。
「う、うん」

お手本と言われても、ぼくも金魚すくいなんてするの、ひさしぶりなんだけど……。
まるいふちにうすい和紙がはられた、プラスチック製のポイの持ち手をつかみながら、ぼくはすいそうのそばにしゃがみこんだ。
すくった金魚を入れておくボウルに水を満たすと、ぼくは目の前を泳ぐ黒い出目金をつかまえようと、ポイを水にひたした。
そっと出目金の下までポイを移動させ、水からすくいあげる。
出目金が和紙の上にのっていた。
「やった!」

ぼくが声をあげたしゅんかん、出目金は尾びれをはげしく動かして体をふるわせる。そのしんどうでぬれた和紙がやぶれ、出目金はすいそうへと落ちていってしまった。
「残念だったな、ぼうず」
店主が大きなわらい声をあげた。
「ダメだよ、陸。真上にあげたらかんたんにやぶれちゃうんだって。ほら、見ててよ、こうやるの」
ゆかたのそでをまくった美鈴ちゃんは、水面に対してななめにポイをつけて、赤くて小さな金魚の下に移動させた。ななめにしたまま水中から出して、和紙の上にのっている金魚をあばれる前にすばやくボウルの中にうつす。
「ほらね」
とくいげにあごをしゃくった美鈴ちゃんは、同じような方法であと二ひきをすくいあげたけど、そこでポイがやぶれてしまった。
「あー、三びきか。もっとつかまえられると思ったのに」
美鈴ちゃんはくやしそうに、和紙がやぶれたポイを店主に返す。
「はいはい、おじょうちゃんおつかれさま。やりかたはわかったかい。がんばりなよ」
からかうように店主は言うけど、天馬君はその声が聞こえていないかのように、あごに手をあてる。
「なるほど、水と和紙の角度がたいせつなんだ。水面に対してななめにしないと、水の重みですぐにやぶれてしまう。それに、和紙は水にとける性質があるから、全体をつけないで、できるだけ水との接触をへらさないと。
そのためには、水面近くにいる金魚をねらって……」

数十秒、ぶつぶつとつぶやいたあと、天馬君はそっとすべらすようにポイを水面にそわせて、金魚のそばまで移動させる。なめらかな動きで、和紙のほんのはしっこだけが水につかり、そこにいた金魚をすくいあげると、あばれる前に左手で持ったボウルを近づけ、その中に入れた。
あまりにもあざやかな一連の動作に、ぼくと美鈴ちゃんの口から思わず、「わぁ」と声がもれた。
天馬君はポイとボウルをたくみにあやつり、次々と金魚をつかまえていく。
二十ぴき以上すくっても、ポイははしっこがちょっとぬれているだけで、全然やぶれそうになかった。
ふと見ると、店主の顔が引きつっていた。
「お、おい、ぼうず。それくらいに……」
かすれ声で店主が言うけど、天馬君は完全にムシして次々に金魚をすくい続ける。ものの数分で、すいそうにいた金魚はほとんど、天馬君が持っているボウルの中へと移動していた。
「あと一ぴき」
天馬君が言うとおり、すいそうの中にはさっきぼくがつかまえそこねた黒い出目金だけが泳いでいた。
天馬君はまるで見せつけるように、ポイ全体を水につけると、出目金をすくいあげる。
水から出された黒い出目金はさっきと同じように、和紙の上で大きくあばれた。和紙がやぶれて、出目金が落下する。ぼくと美鈴ちゃんが「あっ」と声をあげる。
けれど、やぶれた和紙の下には、ボウルがじゅんびされていた。
金魚であふれるボウルの中に、黒い出目金が落下していく。
「これで全部ですね」
青ざめている店主に、天馬君はちょっといじわるそうに言う。
「いやあ、こまりましたね。金魚が一ぴきもいなくなったらもう商売あがったりですね。これからお客さんもふえてくる時間なのに、店じまいとなったらこまるんじゃありませんか」
「……インチキだ」
うつむいた店主が低い声で言った。
天馬君は「はい?」と耳に手をかざす。
「こんなのインチキに決まってる! ポイになんか細工したんだろ。そうじゃなきゃ、こんなにすくえるはずない!」
顔をまっ赤にして立ちあがった店主は、すいそうをまわりこんでこちらがわにやってくると、天馬君のコートのえりもとに手をのばした。
天馬君はあせったようすで、「陸君!」と声をあげる。
ああ、またか……。
ぼくはかたを落とすと、天馬君をつかまえようとしている店主の手を両手で横からつかんだ。
店主が「え?」と声をあげたしゅんかん、ぼくはくるりと体を回転させた。
手首、ひじ、かたの関節がいっきにぎゃくにひねられて、店主の男は「いて
ててて!? なんだこりゃ?」と声をあげる。
「合気道です。おとなしくしてください」
店主の動きを完全にふうじこめたぼくは、ため息まじりに言う。

ぼくのおじいちゃんは、学校の近くにある合気道の道場で師範をしている。
ようちえん生のころから、ぼくはその道場に通い、おとなたちにまじってけいこしていた。放課後、部室で時間をつぶしているのも、夕方から始まるけいこに参加するためだ。
合気道は相手の力を利用してわざをかける。だから、まだ子どものぼくでも、おとなの男の人をたおしたり、つかまえたりすることができた。
「さすがは陸君。最高のボディガードだね」
天馬君は両手を広げながら楽しそうに言う。
「でも、けんかで合気道のわざを使ったことをばれたら、おじいちゃんにものすごくおこられるんだよ」
合気道は他人をきずつけることに使ってはいけない。自分、そしてなによりもたいせつな人を守るために使いなさい。おじいちゃんからは、耳にタコができるくらい、そう言い聞かされてきた。
注意したとき、そいつが思いきりむねをつき飛ばしてこようとしたので、反射的に投げ飛ばしてしまった。ちょっとすりきずができたくらいだったし、相手の子も悪かったので学校ではそんなにおこられなかったけど、おじいちゃんからかみなりが落ちた。
二時間以上せっきょうをされたあげく、『二度とけんかで合気道のわざを使いません』と反省文を書かされた。
「だいじょうぶだよ。これはけんかじゃなくて、ぼくを守ってくれただけだから」
ぼくのかたを軽くたたいた天馬君は、ひねりあげられた関節がいたくてつま先立ちになっている店主を見る。
「おじさん、おちついてください。この金魚、全部持って帰ったりしませんから。こんなにいっぱいはかえませんよ。そのかわり、ぼくの質問にちょっとだけ答えてください。いいですか?」
「わかった。わかったからはなしてくれ」
店主は泣きそうな声をあげる。
天馬君が目配せをしてくるのをかくにんして、ぼくは店主の手をはなした。
自由になった店主は、後ずさりしてぼくからきょりをとる。
「話って……なんだよ?」
「こんな大きなすいそうをじゅんびしているわりには、金魚が少ないですよね。もしかして、昨日、金魚がいなくなったりしませんでしたか?」
天馬君がたずねると、店主は目をまるくする。
「なんで知っているんだ!?」
「ああ、やっぱりここの金魚だったんですね。ちょっとそれについてくわしく教えてください。そうしたら、すくった金魚は全部お返しします。いい取引だと思いませんか」
天馬君のていあんに、店主は苦虫をかみつぶしたような顔で考えこんだあと、「来な」と手まねきをする。
天馬君はほほえむと、ボウルをひっくり返した。
色とりどりのつぼみがいっせいに花開いたかのように、美しい金魚たちがすいそうに広がっていった。

「ここだよ、見ろ」
ぼくたちを屋台のうらに連れてきた店主が言う。
「昨日、八時すぎにお祭りが終わったあと、すいそうをここにいどうさせてビニールシートをかけていたんだ」
よく見ると、おとといの雨でまだ少しぬれている地面に、すいそうが置いてあったあとが残っていた。
「本当はいっぱい金魚がいたんですね」
天馬君は地面を見つめながら言う。
「ああ、百ぴき以上いた。けれど、今朝確認したら、三十ぴきくらいまでへっていた」
「つまり、昨日の夜、だれかが七十ぴきぐらいとっていったということになりますね」
店主は「そうだ」とうなずいた。
「警察に通報はしたんですか?」
「警察? そんなめんどうくさいことするわけないだろ」
「どうしてですか? たいせつな金魚をぬすまれたんでしょ」
「ぬすまれたんじゃない。買いとってもらったんだ」
「買いとって?」
天馬君はふしぎそうに聞き返した。
「ああ、そうだ。ビニールシートの上に、ふうとうに入った金が置いてあった。金魚のねだんとしては多すぎるくらいの金がな」
店主はにやにやとわらった。
「つまり、犯人は今日の商売はできるくらいは金魚を残したうえ、しっかりと代金をはらっていったというわけですか。もはやそれは犯人じゃなくて、お客さんですね」
天馬君は楽しそうに言う。
「ああ、そうだな。これでもういいだろ。おれは店番があるから、あとは好きにしな」
店主は屋台にもどっていく。
「ねえ、天馬君。やっぱりうちの学校のプールにいた金魚って、ここから来たの?」
美鈴ちゃんが質問すると、天馬君はコートの内ポケットから虫めがねをとり出し、はいつくばって地面を調べ始めた。
「やっぱりあった。美鈴君、陸君、これを見なよ」
天馬君は地面を指さす。
目をこらすと、そこにうっすらとふたすじの線が走っていた。
その線は、神社の出入り口に向かってのびている。
「なあに、それ?」
美鈴ちゃんはあごに指をそえた。

「台車の車輪のあとだよ」
天馬君の答えを聞いたぼくは、両手を合わせる。
「じゃあ、犯人は台車でここまで来て、給食用のなべに金魚を入れてプールに運んだってこと?」
「そうだろうね。この神社から学校の出口は近いし、かいだんもない。台車を使ったら、かんたんに金魚を運べたはずさ」
「それで、天馬君はだれが犯人なのかわかったの?」
美鈴ちゃんのしつもんに、天馬君はうでをくんで少し考える。
「プールにいた金魚がここから運ばれたことがわかっただけじゃ、まだ犯人を特定するには情報が足りない。ただ、ちょっとした仮説を思いついたんだ。それをたしかめるために、まずは用事をすませたあと、ちょっと学校にもどろう」
「用事? 用事って何?」
美鈴ちゃんが首をかたむけると、天馬君はにっこりとわらった。
「もちろん、お祭りを楽しむことだよ」
4 夜のおじぞうさん
「ああ、おなかいっぱい。ちょっと苦しい」
キツネのおめんを頭に引っかけた美鈴ちゃんが、ゆかたにつつまれたおなかをなでる。
「あんなに食べるからだよ」
ぼくがあきれると、美鈴ちゃんはほおをふくらませた。
「だって、お祭りの食べ物ってすごくおいしいじゃん。同じやきそばでも、家で食べるのとは大ちがい。やっぱりプロの人が作っているからかな」
「いや、たぶん味自体はそんなに変わらないよ。ただ、お祭りという非日常の空間で食べるという特別感が精神的な調味料となって、おいしく感じさせているんだろうね」
前を歩く天馬君が、また何かむずかしいことを言う。
「うーん、友だちといっしょにごはん食べたらおいしいってこと? 天馬君もおいしかったでしょ」
美鈴ちゃんはちょっと首をかたむけた。
「ああ、もちろんおいしかったよ」
やきそば、たこやき、りんごあめ、チョコバナナ、フランクフルト、わたあめ、ぼくたちはおなかいっぱいになるまで、屋台で売っている食べ物をおなかにつめこんだり、射的やくじ引きを楽しんだりした。
一時間ほど遊んで持ってきたおこづかいが底をつきかけたころ、「そろそろ行こうか」と天馬君が言った。そうしてぼくたちは、ちょうちんで明るく照らされた神社をあとにして、歩いて三分ぐらいのところにある学校にもどってきたのだ。
ぼくは十才のたんじょうびにもらったうで時計を見る。夜の八時半をすぎていた。昼休みには、たくさんの生徒がドッジボールとか一輪車で遊んでいる校庭が、いまは暗く、しんとしずまりかえっていて、なんだか気味が悪かった。
「ねえ、こんな時間に学校に入っておこられないかな」
ぼくは首をすくめる。
「だいじょうぶだよ、陸君。ぼくたちは真理子先生にたのまれて、『金魚の泳ぐプール事件』の捜査をしているんだ。つまり先生の許可があるんだよ。それに、もうひとつの事件も解けるかもしれないしね」
「もうひとつの事件?」
ぼくが聞き返すと、天馬君は「すぐにわかるよ」といたずらっぽくくちびるのはしをあげた。
「あれ? プールはこっちじゃないよ」
校庭のすみに向かって進む天馬君に、美鈴ちゃんが言う。

「プールを見にきたんじゃないよ。こっちこっち」
天馬君はコートの内ポケットから、小さなペンライトをとり出すと、体育館の横にある小さな路地に入る。
「ここだよ」

雑草がはえている暗い小道を照らしながら進んで体育館の横にとうちゃくすると、天馬君はブロックべいでかこまれたスペースを指さした。
そこは、おじぞうさんが置かれている場所だった。
「おじぞうさん?」
美鈴ちゃんがまばたきをする。天馬君は大きくうなずいた。
「そう、真理子先生に捜査をたのまれたでしょ。おじぞうさんをたおした犯人を見つけてほしいって」
「でも、つまらない事件だってことわったじゃないか」
ぼくがしてきすると、天馬君はこめかみをかいた。
「うん、たしかにそう言ったね。だれかふとどき者のいたずらにすぎないと思って。けれど、それはまちがいだったのかもしれない。プールに金魚があらわれたことによって、この事件はたんなるいたずらではなく、大きな意味をもっている可能性が出てきたんだよ。だから、調べる必要があるんだ」
「でも、調べるって言っても、かぎがかかっているよ。中は見られないよ」
ぼくはブロックべいについている、金あみでできたとびらを引く。それはびくともしなかった。あみ目が細かいので、手を入れて内がわにあるかぎを開くこともできない。
「そんなことないさ。外から開かなければ、中から開ければいいんだ。というわけで、美鈴君。たのむよ」
天馬君はブロックべいの上を指さす。二メートルくらいのへいの上には、はり金でできたフェンスがついていた。
「はいはい、りょうかい。ちょっとおなかが重いけど、食べすぎたあとの運動にちょうどいいかも」
ゆかたすがたの美鈴ちゃんはかろやかにジャンプすると、へいの上のフェン
スに手をかけ、いっきにそれをこえようとする。
「ああ、ちょっと待って」
あわてて天馬君が声をかける。フェンスをまたいだところで動きを止めた美鈴ちゃんは、「なあに?」と小首をかしげた。
「そのあたりをよく調べてくれないかな」
天馬君はペンライトでフェンスを照らした。
「調べるって、べつに何も……」
そこまで言ったところで、美鈴ちゃんは小さな悲鳴をあげた。
「どうしたの、美鈴ちゃん!? だいじょうぶ?」
ぼくがあわててたずねると、美鈴ちゃんはふるえる手で、フェンスの上のほうにつき出しているはり金を指さした。
「ここが……、なんか赤い……。たぶん、血だと思う……」
ぼくは「えっ!?」と声をあげると、ブロックべいに近づいて目をこらす。美鈴ちゃんの言うとおり、はり金が赤くそまっていた。
「思ったとおりだ!」
天馬君は大きな声をあげる。
「思ったとおりって、天馬君、ここに血がついているって知っていたの?」
美鈴ちゃんの声はかすれていた。
「知っていたわけじゃないよ。ただ、ぼくの想像が正しかったら、そこにだれかがケガをしたこんせきが残っているはずだと思っていたんだ。やっぱりぼくの推理は合っていたみたいだね」
天馬君はうんうんと、満足げにうなずく。
「それじゃあ、美鈴君。もうそこはいいよ。中に入って、かぎを開けてくれるかな?」
美鈴ちゃんは言われたとおりにブロックべいの内がわに飛びこむと、中からとびらのかぎを外してくれた。
「ありがとう。あとは最終確認だね」
とびらを開いた天馬君は、スキップするような軽い足どりで中に入る。何が起こっているのかわからないまま、ぼくもあとに続いた。
ブロックべいでかこまれたせまい空間には、小さな石のほこらが建っていて、その中に五十センチくらいの大きさのおじぞうさんがおさまっていた。
「さすがに百五十年以上前からあるだけあって、かなり古びているね」
天馬君はほこらに近づくと、まじまじとそれを見つめる。
「ねえ、おじぞうさん、たおれていたんじゃなかったっけ?」
フェンスについていた血を見てこわくなったのか、美鈴ちゃんが小さな声で言った。
「先生たちが元にもどしたんだろうね。おじぞうさんをたおれたままほうっておいたら、ばちがあたりそうだし」
天馬君はコートの内ポケットから虫めがねをとり出した。
「うーん、このほこらはおじぞうさんのサイズに合わせて作られたものなんだろうね。ほら、サイズがピッタリ合っている。少ししかすきまがない。さて、ぼくの推理が正しければ……」
天馬君はひとり言をつぶやきながら、虫めがねでおじぞうさんの足元をのぞきこむ。
やがて、天馬君のほおが小さくふるえ出した。
「はは……、あはは……、あはははは!」
急に天馬君が大声でわらいだす。ぼくと美鈴ちゃんは顔を見合わせてため息をついた。ナゾが解けた天馬君はいつもこんなふうにテンションが高くなり、へんなことを言いだすのだ。
「何かわかったの? 天馬君」
美鈴ちゃんが声をかけると天馬君は芝居じみたしぐさで大きく両手を開く。
「もちろんだよ、美鈴君。これまでに見てきた証拠がひとつの真実をしめしている。ミステリ小説なら『あれ』が入るシーンだね」
天馬君は器用に指を鳴らすと、高らかにせんげんした。





試し読みはここまでになります。続きは本をご購入のうえ、お楽しみください。
いいなと思ったら応援しよう!


